疲れない登山のポイント|山のお悩み相談室 Vol.3
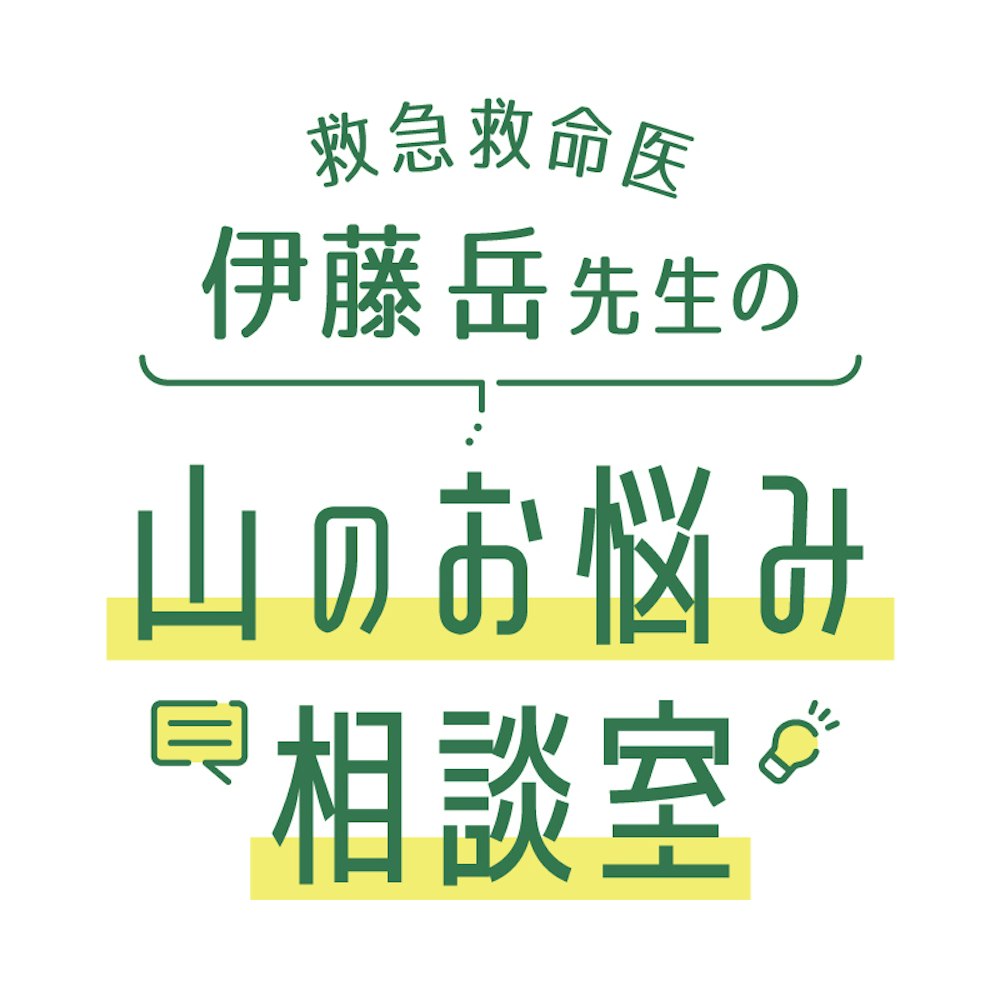
【今月のお悩み】
「登山を軽やかに楽しみたいと思っているのに、いつも山頂に着くころにはヘロヘロになってしまいます……。疲れない登山のポイントや、体力づくりの方法を教えてください!」
登山中の体の不調やお悩みを解決する「登山のお悩み相談室」。第3回目のテーマ「疲労」について救急救命医の伊藤岳先生からお話をうかがいました。伊藤先生によると、医師として北アルプス三俣山荘診療所で夏山診療を行うなか、実際に疲労困憊した登山者たちをよく見かけるそう。疲労の原因はいろいろなものが考えられますが、今回は何はなくとも最低限あるに越したことはない「登山に求められる体力」を中心に、疲労の原因を探っていただきました。
(監修:伊藤 岳、文:池田 菜津美)
【登山に求められる「体力」とは?】

疲労の原因は、体力がないことや、気温が低い・標高が高いといった環境によるもの、体調が万全でないことなど、さまざまに考えられます。今回は最低限あるに越したことはない「体力」を中心に、疲労の原因を探っていきたいと思います。ここでは体力を「筋力」と「心肺能力」の2つに分けて、登山においてはどんなものが必要か、考えてみましょう。
登山で使う筋力には「プラスアルファ」が必要
平地を歩いたり走ったりすることに使う筋力と、登山に求められる筋力はイコールではありません。登りでは身体と装備の荷重を引っ張り上げる筋力が必要で、下りではその荷重を一歩一歩受け止める筋力が求められます。平地での移動に比べ、登りでは足を高く上げなくてはいけませんし、下りでは次の一歩をより低いところに置くことになります。さらに、これらの動きの中で体幹の筋肉(腹筋や背筋など)は、装備も含めた身体全体のバランスを支え続けています。
つまり、荷重を受け止めたり、足を高く持ち上げたり、身体全体を支え続けたりと、登山に求められる筋力は平地で使う筋力だけではなく、プラスアルファの部分があるということ。普段からジョギングやウォーキングをすることは登山にとってもちろんプラスになりますが、それだけではプラスアルファの部分を埋めることはできません。
登山の筋力をつけるにはどうするのがよい?

一番効率がよいのは山道を歩くこと。登山を行うなかで自然と必要な筋力が鍛えられます。不整地特有の足運びも習熟でき、一石二鳥です。でも、誰もが日々山道を歩けるわけではありませんから、日々の生活では積極的に階段や坂道を使うのがよいでしょう。大腿部(太もも)や臀部(お尻)の筋肉に負荷がかかっていることを意識すると、より効果的です。

歩く時間を長くつくれないときは、隙間時間のスクワットをおすすめします。今はインターネットの記事や動画で「正しいスクワット」のやり方が容易に確認できますが、1つだけポイントを挙げるなら、「自分が鍛えようとしている部位、筋肉に負荷がかかっていることを、一動作ごとに意識する」です。屈曲時に腹筋の収縮を意識すると体幹も鍛えられてさらによいと思います。
一度にまとまった回数をこなす必要はありません。無理なく正しく行える回数にとどめましょう。むしろ、例えば歯磨きをしながら、電子レンジの温め中にと、ちょっとした隙間時間を利用し、一日に何度も取り入れた方が効果的で三日坊主の防止にもつながります。
〈おすすめアイテム〉
「脚を鍛える」の一助に|日常生活の歩行を「足指のトレーニング」に変える普段履き用インソール
体力アップに欠かせないのが心肺能力
筋力トレーニングをしていると、心臓の鼓動が早くなったり息切れがしたりして、ペースダウンを強いられることがあります。これは、酸素を血液中に取り込んで身体中に送り出すという、心臓や呼吸の機能にブレーキがかかっているサインです。いくら筋力をつけても、これらの機能に余力が無いと、せっかくの筋力を発揮し続けることはできません。
一定以上の負荷をかけながら20〜30分以上運動を
心肺能力においても、最も効率がよいのは山道を歩くことです。山道を歩くトレーニングは、筋力アップや足運びの習熟に加え、心肺能力の向上も見込めるので、じつは一石三鳥なんですね。トレーニングの負荷は、コース選びやペース、装備の重さなどで調整できます。とはいえ、山道トレーニングを頻繁に行うのは難しいので、手軽に取り入れていくならランニングやウォーキング、水泳や自転車などがよいでしょう。いずれも負荷の調整が容易ですし、自分に合ったジャンルで楽しく続けるというのが大事です。
しかし、比較的短時間でも効果が得られる筋力トレーニングとは異なり、心肺能力のトレーニングは一定以上の負荷をかけながら、20〜30分以上運動を継続する必要があります。隙間時間に都合よく…というのは少し難しいかもしれません。負荷の目安は少し息が切れるくらい。ぜぇぜぇしてしまって、運動が続けられないほどの負荷をかける必要はありません。
【登山で「体力」を無駄にしないためには…?】
1. 無駄の少ない歩き方をしよう!

山で見かける元気な人たちは、あなたよりも優れた体力の持ち主なのでしょうか? ある一定の水準を満たしてはいるかもしれませんが、おそらく全員が並外れた筋力や持久力を有しているという訳ではないでしょう。加齢や疾病、運動不足など、さまざまな要因で体力の維持向上は困難になりますが、いくつになっても変わらぬペースで飄々と登山を楽しんでいる人はいます。
こういった人たちの多くは、無駄の少ない歩き方をしています。大き過ぎない適度な歩幅や、過剰に足を持ち上げないこと、一か所に負担を集中させない技術など、無駄の少ない一歩の積み重ねが、結果として少なからぬ疲労の差となって表れているのです。
2. 柔軟性は身を助ける
登山道は必ずアップダウンがあります。傾斜が急であればあるほど、足関節にはより広い可動域が求められます。関節が柔らかく柔軟性のある人は、より少ない負担で自然に足を運べますが、柔軟性に乏しい人は足の置き方が制限されるため、負担が蓄積されていきます。つまりは柔軟性があると、体力を温存できるということです。
3. 持ちものが増えるほど荷重も増える

天候や気温に合った衣類や装備を選ぶことも大切です。身体が冷えてしまったり、逆に過剰な発汗を招くほど体温が上がったりすることは、いずれもパフォーマンスの低下につながります。
では、さまざまな状況を想定し、それに対応できるウエア・装備を携行したほうがよいのでしょうか? これはみなさんがお考えの通り、過剰なウエア・装備を携行することは決して推奨されません。持ちものが増えて重くかさばるほど、身体と一緒に持ち上げる荷重は増えます。下りではそれだけの荷重を一歩一歩受け止めなければなりません。登山計画を踏まえて、予想される天候や気温、自分の体力やスピード、補給(食事や飲料水)ポイントの有無などから、必要な持ち物を選定しましょう。
しかし、軽さが常に正義であるとは限りません。ザックであればパッキングのしやすさや背負い心地、靴であれば耐久性やサポート力など、軽量化に伴って何らかの機能が低減されていることもあります。軽さだけに飛びつくのではなく、自分の経験値やニーズに合った製品を選ぶとよいでしょう。
〈おすすめアイテム〉
|アクティブインサレーションで気温や体温変化にも1枚で対応
|軽量・高機能なトレッキングポールで快適な山歩きを
|荷物の見直しと整理にスタッフバッグを活用
|収納上手なバックパック
「気のもちよう」と言うけれど…
精神論を掲げるつもりはありませんが、気持ちの問題も疲労に少なからず関与します。気をつかわねばならない同行者の存在、初めてのルート、想定外のトラブル発生といった状況では、時として緊張や焦りが生じ、知らず知らずのうちに疲労の蓄積につながることがあります。いろいろな意味で「余裕のある」登山計画を立てて、気持ちにゆとりをもって動けるようにしたいですね。
まとめ|事前の体力向上と登山中の体力温存を
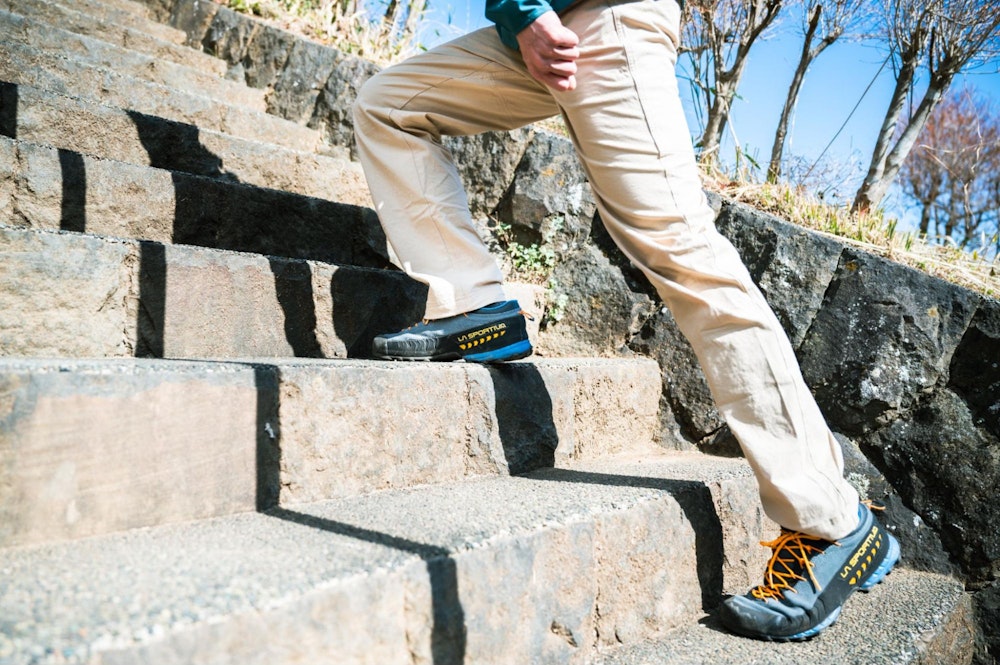
筋力は隙間時間を使ったトレーニングで、心肺能力は一定の負荷を与える運動を楽しく続けることで、向上させていくことができます。また、登山における「体力」は、歩き方や山行計画などで消耗してしまうもの。登山を無理なく楽しむためにも、体力温存を意識して登山の方法を見直してみましょう。
まだある! YAMAPストアの軽量ウェア&山道具
撥水機能を備えた軽量コンパクトなウェアや、強度のあってミニマムなサイズ感の折りたたみ傘など、機能性を備えた軽量ウェア&山道具がたくさん。荷物の重さが気になる人は、装備の買い換えの際には「軽量化」も追加して検討してみてはいかがでしょうか。
〈おすすめの軽量ウェア&山道具〉

伊藤 岳(いとう たけし)
救急救命医 兵庫県立加古川医療センター 救急科部長 公益社団法人日本山岳ガイド協会 ファーストエイド委員 在学中に文部省登山研修所(現国立登山研修所)大学山岳部リーダー研修会三研修を修了。平成13年アイランドピーク登頂、平成21年神奈川大学山岳部チョモランマ遠征登山隊に医師として参加。平成22年より北アルプス三俣山荘診療所で夏山診療に従事。現在山岳ガイド協会では特別委員会コロナ対策プロジェクトチーム医療班メンバーを併任している。












