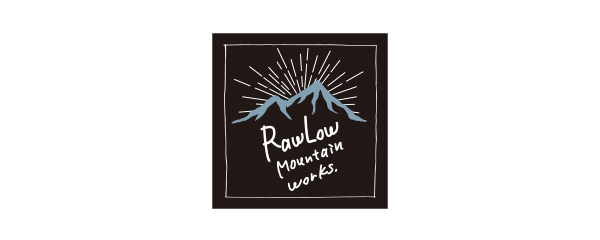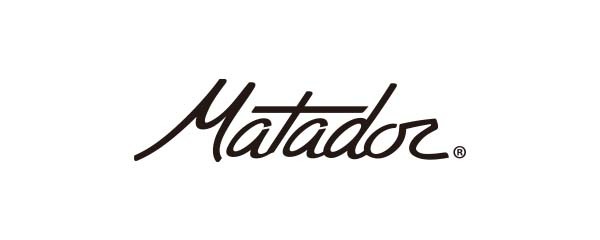秋の日帰り登山|紅葉を楽しむための持ち物ガイド
だんだんと秋が深まり、紅葉シーズンが近づいてきました。
赤や黄色に染まる広葉樹と、緑の常緑樹が織りなす山肌は、植生が豊かな日本の山々ならではの絶景。その景色は、「錦絵巻」と称されるほどです。
今回は、そんな紅葉の山を日帰りで気軽に楽しむための必携&おすすめのアイテムをご紹介。快適かつ安全に、鮮やかな紅葉を楽しみながら歩きましょう。
1. 紅葉ハイキング 季節の注意点・持ち物の注意点

寒暖差に対応したウェアリングが快適さに直結
紅葉は、一般的に朝の最低気温が8℃前後を下回る日が続くと、少しずつ色づき始めます。つまり、紅葉が進んでいるエリアは、都市部でいえば「真冬の朝晩並みの冷え込み」と考えてよいでしょう。
ただし、日中は気温がぐっと上がり、20℃近くまで上昇することもあります。朝晩と昼間の寒暖差が大きいため、重ね着や脱ぎ着しやすい服装を心がけ、体温調整できるように準備しておくことが大切です。
今回はそんなウェアリングをはじめ、日没が早まったり、凍結や降雪の可能性もある秋特有の装備をピックアップ。あわせて見頃のスポットの見つけ方や、紅葉シーズンにおすすめの山を紹介します。
2. 基本の装備
ポイントはアイテムの出し入れとウェアの着脱のしやすさ
日帰り登山ではアイテムは少なくコンパクトに切り詰めたいところですが、前述の通り秋は寒さ対策などでウェアをはじめとするアイテムが嵩張りがちです。
そこでポイントになってくるのが、これらのアイテムのザックからの出し入れのしやすさや、ウェア類の着脱のしやすさです。
ザックは30ℓまで程度の大きさがおすすめ
日帰りということでアイテムの数は多くありませんが、ザックは20〜30ℓ程度の容量がおすすめです。20ℓ未満のザックでも収納しきれないケースは少ないものの、狭い収納スペースに詰め込む結果となってしまいます。
こうなると必要な時に必要なアイテムを取り出すのに手間取ったり、アイテムが迷子になってしまうことも。比較的容量にゆとりがある状態にした上で、アイテム毎に整理整頓しておくパッキングがコツです。
登山用のザックは、この状態でもコンンプレッションベルトなどで厚みや高さを調整できるので、不恰好に見えることはありません。
ミドルレイヤーによる温度調節が快適さに直結
気温が下がり、肌寒さを感じることもある紅葉シーズン。Tシャツ・カットソーなどのベースレイヤーの上に羽織る、ミドルレイヤーのセレクトが、快適な登山のポイントになります。
代表的なアイテムが「ソフトシェル」。適度な厚みがあり保温力に優れている上、生地が柔らかいので身体の動きにもしっかりと追従してくれる上、堅牢性や適度な撥水性も備えています。
とはいえ、標高や時期によっては昼間の行動では暑さを感じる場合も。こうした場面で携行しておくと安心なのがフリースです。かつては厚く嵩張るという印象を持たれがちなフリースですが、着心地の柔らかさや吸湿速乾性はやはり魅力。近年人気の薄手のモデルがおすすめです。
暑さを我慢して行動を続けた結果の発汗が原因の「汗冷え」は、低体温症の原因になりがちです。体感温度によってこまめに着脱できるウェアをセレクトしましょう。
安全のためにもしっかりセレクトしたいベースレイヤー・ドライレイヤー
条件によってかなりの低温になる紅葉シーズンは、低体温症による痛ましい山岳遭難が発生しやすい時期でもあります。気温や標高にあわせて、吸湿速乾性だけでなく保温性も備えた厚手のベースレイヤーも寒さ対策には重要です。
ミドルレイヤーと同様に「汗冷え」を防止するため、ドライレイヤーは気温差が激しい紅葉シーズンも着用しておきたいウェアです。
シューズのセレクトはフィールドにあわせて
宿泊登山と異なり、荷物が少ない(軽い)日帰り登山においては、必ずしもハイカット・ミドルカットのモデルを履く必要はありません。軽量な装備で短時間の行動であれば、ローカットでもOKです。
岩場や滑りやすい急斜面であればグリップ力の高いアプローチシューズ系、標高差が少なく自ずと歩行速度が上がるハイキングであれば推進力の高いトレイルランニングシューズ系など、フィールドにあわせたソールのモデルをセレクトするのもおすすめです。
3. 秋の日帰り登山 必携アイテム

紅葉狩りという言葉通り観光気分で山に入る人も増える一方、低温や日没の早さなどから秋は山岳遭難も増加するシーズンでもあります。安全を考慮した、以下のアイテムも必携です。
ヘッドランプは日帰りでも必ず携行

冬至にかけて加速度的に日没が早まる紅葉シーズン。明るいうちに下山する日帰りの登山計画でも、ヘッドランプは必ず携行しましょう。ケガや道迷いなど何らかのトラブルで時間をロスしてしまう場合もありますし、そもそも樹林帯では日没の1〜2時間前でも足元が薄暗くなって、転倒などの原因になりがちです。
レインウェア・スパッツのセレクトも重要

天候によっては冷たい風雨にさらされることもある紅葉シーズン。どんなに優れたベースレイヤー・ミドルレイヤーを着用していても、低体温症の原因となる「身体の濡れによる冷え」を防止する最後の砦が
レインウェアです。
また、風速も1m/s上がるごとに体感気温は約1℃低下します。雨が降っていなくても風が強い場合にはウィンドブレーカー代わりにもなってくれます。
靴内に雨が浸入することで、足元から低体温症になるリスクもあります。雨天時はスパッツ(ゲイター)も装着しましょう。ちなみに雨天時のスパッツの装着位置は、レインパンツの内側(外側は降雪時)です。こうしておかないとスパッツとレインパンツの隙間から雨が浸入する原因になります。
特にローカットモデルの靴をセレクトした場合は、登山前にスパッツも一緒に装着してみて、靴との間に隙間がないかをチェックしておきましょう。
防寒用の小物類

気温・風速や地形にもよりますが、山頂などで休憩のため行動を休止する時は、寒さを感じやすいタイミングでもあります。ビーニー・ネックウォーマーなどで寒さ対策をしっかり行いながら、休息をとりましょう。
特に指先は思った以上に冷えや乾燥を感じやすく、ひどい場合は凍傷になることも。手袋は防寒性と防水性の両方を考慮してセレクトしましょう。
また手首の保温も指先の冷え防止には有効です。HOUDINI(フーディニ)パワーリストゲイター/UNISEXは、優れたストレッチ性と通気性で手を快適な環境にキープしてくれます。
モバイルバッテリー

YAMAPアプリなどでのルート確認や天気情報の取得など、現代の登山においてスマートフォンは必需品です。気温が低い紅葉シーズンは電力消費も激しくなるので、モバイルバッテリーは必ず携帯してください。コンパクト&軽量なバッテリーを複数携帯するのも、故障時などを考えると安心です。
アイゼン(滑り止め)

秋と冬の境目ともいえる紅葉シーズンは、思わぬ降雪に見舞われることも。そうでなくても朝晩の低温で、登山道が霜や氷で凍結してスリップを誘発することも。コンパクトに収納できるチェーンスパイクアイゼンのような滑り止めを持参しておくと安心です。
4. 快適さアップ!あると便利なアイテム

アイテムのこまめな出し入れに大活躍のサコッシュ類
紅葉シーズンの登山では手袋などの防寒小物やサングラスなど、アイテムを頻繁につけ外す機会が多いもの。こうしたシーンでいちいちザックを下ろさずにアイテムを出し入れできるのがサコッシュです。
MOUNTAIN HARDWEAR(マウンテンハードウェア)/YAMAP別注 2WAYサコッシュは、底部にマチを配した見た目以上の収納性がポイント。しかも2WAY仕様で裏面のポケット内側に縫い付けられた大容量ショルダーバッグを広げれば、ウェアの収納も可能です。
RIDGE MOUNTAIN GEAR(リッジマウンテンギア)/サコッシュは、必要最低限の容量と機能やパーツで構成されたムダのないアイテムながら、ファスナー・フック・ループなど細かなディテールの工夫で、使いやすさが光ります。
Okara(オカラ)/トムテエコパック/UNISEXは、普段使いしてもお洒落なサイズ感とデザインが魅力。耐久性や防水性に優れながら、100%リサイクルポリエステル原料の環境配慮型の素材を本体に採用している点も注目です。
RawLow Mountain Works(ロウロウマウンテンワークス)/タビチビエックスパック/UNISEXは、底部と天部に大きなマチが設けられており、サコッシュとしてだけでなく広げてトートバックとしても使用可能。収納するアイテムの数や嵩によって、大きさを自在に変える事ができるのも魅力です。
他のアイテムも便利に収納!ポーチ・ケース類

紅葉が美しい山を撮影する際のカメラケースとしておすすめなのがMatador(マタドール) カメラベースレイヤー 2.0/グレーです。防水性・堅牢性に優れた生地はもちろん、様々なカメラアクセサリーを収納できるポケットも配置。何よりカメラの取り出しやすさが秀逸で、絶景のタイミングを逃しません。
PAAGO WORKS(パーゴワークス) スナップ/UNISEXは、ザックのチェストストラップへ簡単に装着できるポーチ。スマホ、カメラ、サングラス、日焼け止めなど様々なアイテムをノールックですぐに取り出すことができます。
収納用スタッフサック
ザックの項目でも述べましたが、アイテムをこまめに出し入れしやすいパッキングが、快適な紅葉登山のポイント。用途や使用シーンによって分類して、それらに合ったサイズのスタッフサックに入れておくのがおすすめです。
スムーズな収納ができたり、使用する際にすぐ取り出せることは、余分な静止時間に身体が冷えてしまうことを防止するためにも重要です。
温かい食事・飲み物でほっこり

気温が下がる紅葉シーズン、休憩時に温かい食べ物や飲み物を口にすることもおすすめ。身体が内側から温まるだけでも、気持ちにゆとりができて登山を満喫できますよ。「コンビニ飯だと味気ないけど、山で調理するのは面倒…」という方には、「保温ボトル+アルファ米+コーヒー」がおすすめ。NO調理で、手軽に温かい食事をゲットできますよ。
YAMAP(ヤマップ)/オリジナル テンピークスクリューマグボトル 500mlは、国内最強レベルの保温・保冷力が特徴。熱々のお湯を入れれば「6時間後でも80度」をキープしてくれます。
YAMAP(ヤマップ)山で飲みたいコーヒー/3種6個入りスペシャルセット/コーヒーバッグで、登山中に優雅なカフェタイムを過ごすのもよし。
Onisi(オニシ)アルファ米 エスニックセット ビリヤニ・ナシゴレンはお湯を入れるだけで本格的なエスニック風味の米料理が出来上がり、異国情緒を満喫できる絶品グルメです。
よりオーソドックスな味わいがお好みであれば、Onisi(オニシ) アルファ米 五目・わかめ・ドライカレー3個セットがおすすめですよ。
もちろん、山での調理を手軽にしてくれるアイテムもあります。PAAGOWORKS(パーゴワークス)トレイルポットは、様々な調理法をこなす万能深なべ。ガス缶と調理道具をスッキリ収納できるので持ち運ぶのも楽ちんです。
5. 安全に紅葉登山を楽しむポイント

天気予報や日没時刻は必ず事前にチェック
繰り返しになりますが、天候次第では低体温症のリスクが高い紅葉シーズン。天気予報をよくチェックして、低気圧通過中や通過後の暴風雨や、等圧線の間隔が狭い時の強風が予想される時には、登山を見合わせるのが賢明です。
もちろん日没時間も必ずチェックして、遅くとも日没の2時間前を目安に行動終了できるような計画を立てる事が重要です。
無理なく楽しむことができる山選びを
秋は落葉によって登山道が隠れてしまい道迷いを起こしたり、落葉の下の路面状況が分からずにスリップ・転倒してしまうことも。こうした場所では、慎重に次の一歩を踏み出すか、落葉をかき分けて路面の状況を把握してから歩みを進めるのがポイント。落葉を除けたり安定した歩行のために、トレッキングポールの使用も有効です。
またそもそもこうしたリスクが少なく登山者が多い整備されたコースや、初心者向けのコースを選ぶことも大切です。場合によっては、ケーブルカーやリフトを活用するのも賢いチョイスでしょう。
リアルタイム紅葉モニターを活用しよう!
紅葉の見頃を逃さないために、YAMAPでは「リアルタイム紅葉モニター」をお届けしています。アプリダウンロード数520万を誇るYAMAPのビッグデータを用い、全国25,000座を徹底分析! きっとお目当ての紅葉が見つかるはずです。

6. 鮮やかな絶景が広がる!全国の紅葉名山を紹介
しめくくりに全国の紅葉名山をご紹介。あなたのお住まいのエリアから、日帰り可能な紅葉名山を探してみて下さい。
チセヌプリ(北海道)|紅葉の見頃は例年10月上旬〜10月中旬

紅葉の神仙沼(Ryoさんの活動日記)
ニセコ連峰のほぼ中央に位置するチセヌプリ(1,134m)。アイヌ語で「家のような山」を意味する通り、屋根のような形をした山頂が特徴的で、山頂からの眺望も秀逸です。
しかし何といっても魅力的なのは、山頂直下の沼を筆頭に、登山道沿いに点在する長沼・神仙沼などの湖沼。長沼の広大な水面はチセヌプリを美しく映し、神仙沼周辺の紅葉はひときわ鮮やかです。
栗駒山(宮城・岩手・秋田県)|紅葉の見頃は例年9月下旬〜10月上旬

紅葉の栗駒山(mSngkzさんの活動日記)
東北随一のみならず、全国でも指折りの紅葉名山として知られているのが栗駒山(1,627m)。山肌全体をカエデ・ドウダンツツジ・ナナカマドなどがカラフルに染め上げ「神の絨毯」と呼ばれる絶景です。
様々な登山コースがありますが、岩手県側の昭和湖付近は火山活動により立入禁止となっているため、宮城県側のいわかがみ平からのコースがおすすめ。ただし紅葉シーズンはマイカー規制のため、WEB事前予約制のシャトルバスを利用して下さい。
乗鞍岳(長野県・岐阜県)|紅葉の見頃は例年9月下旬〜10月上旬

乗鞍岳の紅葉(さこ35さんの活動日記)
北アルプスの南にそびえ、長野県側の乗鞍エコーライン・岐阜県側の乗鞍スカイラインという山岳道路(マイカー規制のためシャトルバスや認可を受けたタクシーへの乗換が必須)で標高2,702mの畳平まで歩かずアクセスできるのが乗鞍岳(3,026m)です。
山頂周辺はガレ場が続きますが、見下ろす山肌はまさに錦模様。槍・穂高連峰をはじめとした山岳パノラマも見事です。とはいえ標高が高く低体温症リスクも高い山。万全の防寒対策が必要です。
那須岳(栃木県)|紅葉の見頃は例年9月下旬〜10月上旬
三頭山(東京都)|紅葉の見頃は例年10月中旬〜11月上旬

紅葉に包まれた三頭大滝(Tommyさんの活動日記)
東京都内でありながら豊かな自然に恵まれた奥多摩エリア。その中でもブナの天然林をはじめ広葉樹が多く、紅葉がひときわ美しいのが三頭山(みとうさん・1,531m)です。
その山名の通り西峰・中央峰・東峰の3つの峰から構成され、西峰からは東京都最高峰・雲取山や富士山も眺望できます。山懐は都民の森として散策路が整備され、三頭大滝から延びる森林セラピーロードというウッドチップの道が快適です。
竜ヶ岳(三重県・滋賀県)|紅葉の見頃は例年10月中旬〜11月中旬

竜ヶ岳の紅羊(NARIさんの活動日記)
中京圏からアクセスの良い鈴鹿山脈。紅葉名所として有名なのはロープウェイも架設された御在所岳(1,212m)ですが、ちょっと変わった紅葉風景を楽しむことができるのが竜ヶ岳(1,099m)です。
草原状になっている山頂付近に点在しているのはシロヤシオというツツジの一種。春は白い花を咲かせ「白羊」と呼ばれますが、秋にはその葉が真紅に色づき「赤羊」の群れとなって山肌を彩ります。
大台ヶ原山(奈良県・三重県)|紅葉の見頃は例年10月中旬〜下旬

大蛇嵓の紅葉(ゆ〜いちさんの活動日記)
日本有数の多雨が育む豊かな自然が魅力の大台ヶ原。その最高峰である大台ヶ原山(日出ヶ岳=ひでがたけ=1,695m)周辺は、その豊かな植生が織りなす色鮮やかな紅葉と、正木峠付近の伊勢湾台風をきっかけとした枯木と笹原の光景のコントラストが印象的です。
稜線からは尾鷲湾の輝く海も望むことができ、山頂付近は木製階段や展望台も整備されています。また南西に位置する大岩壁・大蛇嵓(だいじゃぐら)から見下ろす紅葉のスケール感は、関西有数の秘境にふさわしい光景です。
比婆山(広島県・島根県)|紅葉の見頃は例年10月中旬〜11月上旬
大船山(大分県)|紅葉の見頃は例年10月中旬〜11月上旬

大船山・御池の紅葉(いへいさんの活動日記)
九州本土最高峰・中岳(1,791m)を中心に連なるくじゅう連山は「九州の屋根」と呼ばれており、標高1,700m級の山々が連なっています。初夏に咲くピンクのミヤマキリシマが有名ですが、秋の紅葉も見事です。
特にくじゅう連山の西部に位置する大船山(たいせんざん・1,786m)は山頂直下にある火口湖では唯一水をたたえた御池が独自の景観を作り出しています。神秘的な青い水面を紅葉が取り囲む絶景は、ぜひ写真に納めたい光景です。
気軽な日帰り登山で紅葉を満喫しよう!
今回は紅葉シーズンの日帰り登山に備えて、基本的な装備・持ち物から便利グッズ、おすすめスポットまでを紹介しました。
ヨーロッパアルプスならカラマツの黄色、カナダのメープル街道ならカエデの赤色と単一種が多い海外と比べても、豊かな植生ゆえの日本独特のカラフルな紅葉は、世界に誇るべきものです。
そんな絶景を快適に楽しむために、しっかりと準備をして安全な登山を心がけてください。