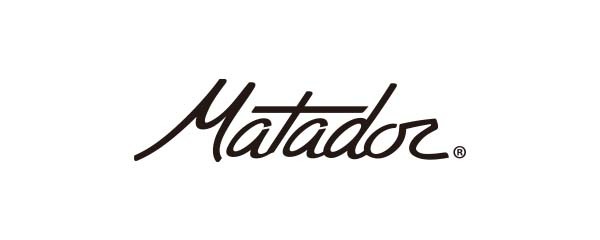夏の日本アルプス登山・初めてのテント泊に準備したいアイテム紹介
いよいよ夏山シーズン到来!
これまで日帰り登山を楽しんできた人の中には、「次のステップ」として宿泊をともなう山行にチャレンジしてみたい、という方も多いのではないでしょうか。
中でも、雄大な自然との一体感を得られるのが、テント泊。テント越しに広がる星空の下で眠り、澄んだ山の空気を肌で感じながら過ごす。そんな、山でしか味わえない特別な体験がそこにはあります。
今回は、特に山のスケールが大きく宿泊をともなう行動が必要な日本アルプスを例に、テントに泊まっての登山に必要な装備や便利なアイテムを紹介。初めてのテント泊にチャレンジする人は必見です!
日本アルプスでのテント泊の魅力と準備の大切さ

テント泊でその魅力を存分に満喫したい日本アルプス
険しくも気高い岩峰や可憐な高山植物が彩るお花畑など、スケールの大きな大自然の絶景を満喫できるのが日本アルプス。まさに「日本の屋根」という表現がぴったりの山域ですが、テント泊初心者には例年7月下旬〜10月上旬が、雪の影響を受けない短い登山ベストシーズンです。
山中で一夜を明かすことは、夕焼けや朝焼けに染まる荘厳な稜線・満天の星空・幻想的な雲海などの絶景を目の当たりにできるチャンス。特に、テントに宿泊することで風のそよぎや野鳥のさえずりなどをリアルに感じ取ることができ、自然との一体感を満喫できることでしょう。

テント泊ならではの事前の準備や装備も大切
とはいえ日本アルプス山中でのテント泊は、テントが張りやすいよう整地された地面や水道・炊事場などが整備されたレジャー向けのキャンプ場のようにはいきません。それなりの準備・装備・スキルが必要なのです。
例えば山頂近くや稜線など標高が高い場所でテント泊するには、真夏であっても朝晩の防寒対策が必要な場合があります。またガレ場・砂礫地など様々な地面に着実にペグを打ち、強い風にも対応できるよう張り綱をしっかり固定するなど、テント設営自体のスキルも要求されます。
今回はそんな日本アルプスでのテント泊をより満喫するため、必要な持ち物や快適グッズの紹介、テント場での基本的なマナーや豆知識、おすすめのテント場とそこに宿泊するコースを紹介します。
テント場までの登山で必要な基本装備

ポイントは「山での生活をまかなうアイテム」をすべて背負って歩くこと
落語の有名な演目・寿限無に「食う寝るところに住むところ」というフレーズがありますが、登山においてこれらにあたる食事・寝具・居住スペースを提供してくれるのが山小屋です。
一方、テント泊では食事のための食糧・燃料・炊事用具・食器から、寝具となるシュラフ(寝袋)や、居住スペースとなるテントなどを、テント場(キャンプ場・野営場などと呼ぶ場合も)まで、すべて自分で背負って歩く必要があります。
ザックは50ℓ以上の容量が必要
食事や寝具が提供される山小屋泊であれば、ザックは30ℓ前後の容量で十分ですが、前述の通りテント泊ではザックへ収納するアイテムが一挙に増えます。
ペアやグループなど複数人でひとつのテントに宿泊する場合であれば、比較的体力がある人は常に必要なテントを、体力がない人や経験の浅い人は日数が経過するにつれて減っていく(軽くなる)燃料・食糧を…などのように分担して持つことでひとりあたりのアイテムを減らすことが可能な場合も。こうしたパターンは40ℓ前後のザックで対応できる場合もあります。
ただしソロ登山やグループでもそれぞれのテントで宿泊する場合は、最低でも50ℓ以上の容量が必要。長い日数の縦走などでは、さらに大きな容量が必要な場合もあります。こうした大型のザックは、収納スペースおよびアイテムの取り出し口が上下に分かれている「2気室」タイプのアイテムが便利です。
登山靴はグリップ力が高いソールとハイカットがGood
日本アルプスの多くの山は森林限界上にあるため、登山道は基本的に岩が重なったガレ場となります。段差や浮石による転倒・スリップ防止のために、グリップ力の高い靴底の登山靴がおすすめです。
また、重いザックを背負っている上半身を支えながら、こうしたガレ場を通過する足首の保護や歩行の安定性を考慮すると、ハイカットのタイプが安心です。
また、このような登山靴で普段から履き慣れているモデルでも、テント泊の重装備を背負うと足に違和感やストレスを感じる場合も。BMZ(ビーエムゼット) YAMAP別注 山を歩くインソール ベーシックは、独自の「Cuboid理論」で、足が本来備えている性能をサポートしてくれます。
レインウェアのセレクトも重要
前述の通り森林限界上の日本アルプスの登山道は木陰がないため、風雨を直接浴びることになります。防水透湿性を備えたレインウェアは、例えば風が強い場合にはウィンドブレーカー代わりにもなってくれます。
またアップダウンの大きな日本アルプスでの激しい行動は、素材の透湿性だけでは蒸れの解消が追い付かない場合も。内部の蒸れを一気に発散できるベンチレーションの有無など、細部のパーツだけでも快適さが大きく変わります。
紫外線対策も抜かりなく
標高が1,000m上がると、紫外線の強さは約10%増加します。標高3,000m級の北アルプスでは低山以上に紫外線対策が重要。サングラス・通気性のよい帽子などを着用することは、熱中症の防止にも有効です。
テント泊での必須装備

テント
登山中の「住居・シェルター」となる基本アイテムがテントです。本体の生地自体に防水性があるシングルウォールと、防水性がない本体生地にフライシートという防水性生地を被せるダブルウォールの2種類があります。
シングルウォールは軽量・コンパクトな反面、低温環境では呼気などで結露するデメリットも。ダブルウォールはフライシートが増えるため重量や収納スペース面では劣りますが、テント本体とフライシートの間のスペースに「前室」を確保することで、収納や作業スペースにすることができます。いずれの場合も、日本アルプスでの登山前にしっかり設営方法を練習しておきましょう。
寝具類
テント泊において布団の代わりになるのが寝袋(シュラフ)。夏でも朝晩は気温が下がる日本アルプスでは、いわゆる3シーズン用のモデルがおすすめです。封入されたダウンの性能や水濡れへの強さ、顔周りのディテールやジッパーの使い勝手などをチェックしましょう。
アイテム数は増えますが、テント場の地面に凸凹や小石が多い時にストレスを軽減してくれるマットや、より快適な睡眠をサポートするエアピロー(枕)などを併用してもよいでしょう。
調理器具
テント泊での楽しみのひとつが、自分の好きなレシピでの食事づくりです。バーナー(クッキングストーブ)の燃料は、寒さに強いホワイトガソリンのタイプと、OD缶と呼ばれるアウトドア用のガス缶のタイプがあります。安全性や扱いやすさの観点から、夏の日本アルプス登山で初心者が使うのであれば、OD缶タイプが断然おすすめです。
調理を行うクッカー(鍋・フライパンなど)は様々なタイプがありますが、昨今はザックに収納する際に無駄なスペースができにくい角形タイプが人気です。PAAGO WORKS(パーゴワークス) トレイルポットシリーズは、2種類のサイズ展開で重ねて収納することも可能。さらにその中にOD缶・食器・食材など様々なモノを収納できるスグレモノです。
テント泊登山の基本アイテム

基本的なアイテムは、山小屋泊登山とあまり変わりありません。ただし重い荷物を背負っての行動や、自然の影響をダイレクトに受けるテント泊であることを考えると、ソックスの強靭性やウェアの保温性がより高いアイテムをチョイスすると良いでしょう。
着替え一式
山小屋では夏でも乾燥室などで濡れたウェアを乾かすことができる場合もありますが、テント泊では不可能。汗で濡れたり汚れたままのウェアで就寝したり翌日も行動を続けることは、不快なだけでなく汗冷えの原因にもなります。
特に肌に直接触れるドライレイヤー・ベースレイヤー・インナー・靴下などは、最低1セットは着替えを用意しましょう。また、これらは密閉できる防水性の袋に入れて保管してください。天候次第では低体温症のリスクもある北アルプスでは「乾いた衣服に素早く着替えられるか」が、重症化を防ぐターニングポイントといっても過言ではありません。
下着類
沢沿いなど水が豊富な山小屋では入浴できる施設もありますが、あくまでも宿泊者専用。山中に湧き出る秘湯に位置しており、外来客も利用できる野天風呂がある山小屋でない限り、テント泊の登山者が入浴できる機会は皆無に近いのが実情です。
前述の着替えの中でもいわゆる下着類のセレクトは、快適さに直結します。吸水速乾性だけでなく抗菌性・防臭性など生地の性能に着目したり、汗ふきシートや制汗スプレーの併用などもおすすめです。
山を歩く女性用に開発された下着が、こちらのHogara(ホガラ)/YAMAP別注 吸水ショーツです。トイレに行ける回数が多くない登山シーンで、女性ならではの悩みを解決してくれるアイテムです。
防寒グッズ
標高が1,000m上がると気温は約6℃低下します。標高3,000m級の北アルプスでは、朝晩を中心に寒さを感じることもあります。特にテント場での休憩・調理・就寝時のように静的シチュエーションでは、フリースやインナーダウンなどの防寒着が重宝します。着用しない時にコンパクトに収納できるかもチェックポイントです。
また稜線上の山小屋で御来光や朝焼けを待つタイミングは、ワクワクすると同時にかなり気温が下がる時間帯でもあります。ビーニー・ネックウォーマー・手袋などで寒さ対策をしっかり行いながら、絶景を楽しみましょう。
その他の小物類
日本アルプスのテント泊登山では、テント場が重要な給水ポイントになります。鞍部や谷間に位置しており水が豊富でじゃぶじゃぶと湧水が流れている水場もあれば、水栓・水槽などを備えた洗面所のような水場もあります。
また、稜線上にあるため水場がなく、予め溜めた天水(雨水)を有料で購入する場合もあります。いずれにせよ調理や翌日以降の行動に必要な水分量を考慮して、水筒・ボトルなどを用意しましょう。
それなりのスペースがある水場であれば、洗顔や歯磨きをすることが可能です。乾きやすいタオルや薄手の手ぬぐい、歯ブラシなどを持参しましょう。環境負荷を考慮して、多くの水場では洗面所があっても石鹸や歯磨き粉は使用禁止です。アルコール除菌剤やタブレット歯磨き粉などを利用すると、快適ですよ。
当然のことながら、山小屋と違いテントには照明設備はありません。夜中にトイレに行きたい時や、夜明け前にパッキングする時に備えて、ヘッドランプは枕元において就寝するようにしましょう。
ただし光量が限られており電池切れの心配もあるため、夜間にテント内をより明るくしたい場合は、ランタンの使用ももおすすめです。CARRY THE SUN(キャリー・ザ・サン) YAMAP限定ウォームライトは、コンパクトに折り畳み可能でソーラー充電できる、アウトドアだけでなく災害時も心強いアイテムです。
またテント内での就寝中は、風にテントがあおられてバタついたり、雨粒がテントやフライシートを叩いたりする音が意外と気になるもの…初心者であればなおさらです。こうした際にはイヤープラグ(耳栓)を用意しておくと安心。近くのテントや山小屋泊で同部屋になった人のイビキや歯ぎしり対策にも役立ちますよ。
また、YAMAPアプリなどでのルート確認や天気情報の取得など、現代の登山においてスマートフォンは必需品です。山小屋に宿泊すれば充電ブースやコンセントを利用できる場合もありますが、テント泊ではそうはいきません。モバイルバッテリーは必ず携帯してください。コンパクト&軽量なバッテリーを複数携帯するのも、故障時などを考えると安心です。
収納用スタッフサック
このように、必要なアイテムが増えるテント泊登山。用途や使用シーンによって分類して、それらに合ったサイズのスタッフサックに入れておくのがおすすめです。スムーズな収納ができたり、使用する際にすぐ取り出せるので、パッキング上手な登山者になれます。
快適さアップ!あると便利なアイテム

ここからは、さらに快適なテント泊をサポートしてくれる、便利なアイテムを紹介します。いずれも、ひとたび使ってみると必需品になること請け合いですよ。
小型のバックパック
山頂を往復する際に重宝するのがアタックザックなどのいわゆる小型のバックパック。山麓・中腹・山頂直下のテント場へテントを設営したら、余分な荷物はベースキャンプとなるテント内に置いて、貴重品・カメラ・雨具・行動食や水分など必要最小限の装備を収納します。
セレクトにあたっては、軽量かつ使用シーン以外ではコンパクトに収納できるモデルがおすすめです。
ただし、テント内のスタッフサックなどにアタック時に不要なアイテムを収納して、そこまで背負ってきたザックでアタックしてもOK。大型ザックのしっかりした背面が、転倒などの際に背骨を保護してくれる場合もあります。
パーゴワークスのZENNは、フロントポケットのように見える外側のパックを外して、取り外し可能なハーネス部分を付け替えることで、5リットルの小型サブパックとして使うことができます。
ゴミ袋用スタッフサック
テント場を管理している山小屋で購入した飲料の空き缶などは回収してくれますが、登山中に出たゴミはすべて登山者自身が持ち帰るのがマナーです。しかし通常のビニール袋では、ガサついたり、中身が透けて恥ずかしかったり、時には破れてしまいゴミを飛散させてしまうことも。
YAMAP(ヤマップ) オリジナル スタッフサックはシンプルな色・デザインと堅牢性・耐久性の高い素材が特徴のスタッフサック。手提げ部分がバックルで開閉できるので、岩場など両手を使うシーンでは素早くザックのベルトなどに装着可能です。
また、テント内では太さ2〜3mm程度の細引き(登山用品点で切り売りで購入可能なロープ)を天井に張って、そこに手提げ部分で吊り下げておくのもおすすめ。限られたテント内のスペース、床だけでなく天井までの空間全体をうまく活用するのが、快適なテント泊のコツです。
テント場でのプチ移動に便利な財布&サコッシュやサンダル
不安定な電波状況などの環境から、現在でも多くの山小屋ではクレジットカードやスマホ決済ではなく、現金でテント泊料金や軽食・飲料・土産物代などを支払います。また宿泊せず休憩で立ち寄った山小屋でトイレを利用する際にも、協力金の支払いが必要です。
RIDGE MOUNTAIN GEAR(リッジマウンテンギア)/Rジップウォレットはは、極力シンプルなデザインを追求した手のひらサイズのジップウォレット。8mmという驚きの薄さで、胸ポケットやヒップポケットに入れても違和感を感じずに行動できます。4辺のうち2辺をファスナーにすることで、大きな間口を確保。小銭も出し入れしやすい形状が特徴です。
また、テントを設営し終えたら、山小屋の売店・トイレなどへはなるべく身軽に移動したいもの。そうした際に財布・スマートフォンなどの貴重品をまとめて持ち運べるのが、サコッシュなどのポーチ類です。
PAAGO WORKS(パーゴワークス) YAMAP別注 スイッチは、ショルダーバッグやチェストバッグなど様々な用途に対応するマルチポーチ。ザックへ取り付けることもできるので、登山中にも利用できます。
そのほかの便利アイテムとして紹介したいのが「サンダル」。
テントを設営したあと、テント場内を移動するときに、毎回ハイカットの登山靴を履き直すのは少し面倒ですよね。そんな場面では、軽量でコンパクトに収納できるサンダルがあるととても便利です。
ただし、ガレ場のような足場の悪いテント場や、暗くなってからの移動時は要注意。実際に、サンダルでの移動中に転倒してケガをするケースも報告されています。
夜間や不安定な場所では、ヘッドランプを使って足元を確認しながら、慎重に歩きましょう。
浄水器
テント場以外で給水ポイントとなるのが、沢や伏流水が湧き出している場所にある天然の水場です。YAMAPアプリや登山地図などで「水場」の表記があれば基本的にはそのまま飲用可能ですが、そうした表記がない場所や、豪雨の後で濁っていて飲用が不安な場合も。
KATADYN(カタダイン)ビーフリーACは、バクテリアを99.9999%、微生物を99.9%除去可能なホロファイバーフィルターに加え、活性炭フィルターを使用することで安全かつおいしい水にすることが可能。山小屋で購入した天水(雨水)の風味が気になる時にもおすすめです。
テント場を利用する時の注意点とマナー
ここからは初めてテント泊にチャレンジする人の不安を解消するため、利用時の注意点やマナーを紹介します。

事前予約の是非をチェック
かつてのテント場は、ほとんどの場所が予約不要でした。しかし大人数でひとつのテントに宿泊するスタイルから、少人数やソロで宿泊するスタイルの変化にともなって、必然的にひとつのテント場に設営されるテントの数が増えるようになりました。
このため、特に稜線上などでテントを設営できるスペースが狭いテント場では、そこを管理する山小屋への事前予約が必要なケースも増えています。事前予約の有無、そして有りの場合は予約開始日(利用日によって変わることが多い)・予約方法(電話・専用サイト・ポータルサイトなど)を確認して、早めに予約しましょう。人気のテント場で夏山シーズンの週末などは、あっという間に予約が埋まってしまう場合もあります。
テント泊の一般的な流れ
日本アルプスに限らず、夏山は午後になると雷雨のリスクが高まります。雨の中でのテント設営は苦労するだけでなく、大切なアイテムを濡らしてしまう場合もあります。また、雷雨時のテント場は落雷の危険性があるので、テントでなく最寄りの山小屋など頑丈な建物へ避難してください。
テント設営や食事の調理などを考えると、遅くとも日没3時間以上前には宿泊するテント場に到着するよう登山計画を立てたいものです。予約不要なテント場の場合はなおさらで、山小屋やトイレに近い「便利な」場所は早い時間に埋まってしまいます。
テント場に到着したらすぐにテントを設営したいものですが、これはマナー違反。まずは受付を済ませましょう。
多くのテント場は管理する山小屋の玄関にカウンターがあり、登山靴を脱がずに受付できます。大規模なテント場では、テント泊専用の管理棟がある場合も。まずはここで受付票の記入やテント泊料金の支払いを行います。この手続きが終わると、受付済を示すカードなどの目印を渡されます。また狭いテント場などでは設営する区画を指定されることもあるので、それに従って下さい。

テント場では設営に邪魔になる小石を移動させる程度で、排水のために溝を掘ったり植物を引き抜くなど地形や植生を変えてしまうような行為は厳禁です。テントを設営したら、先ほどもらった受付済を示すカードなどの目印を、テントの目立つところに括り付けておきましょう。
その後は、トイレ・水場などの場所をチェックしたり、炊事用の水を確保しながら、軽装でテント場をしばらく散歩するのがおすすめ。こうすることで、テント場までの登山で酷使してきた筋肉を少しずつクールダウンすることができます。
これらを終えたら、誰にも邪魔されない自由な時間です。のんびり昼寝や読書をするのもよし、手の込んだ山ごはん作りに向けて下ごしらえに精を出すもよし、近くにテントを設営した隣人と山談義に花を咲かせるもよし…。好きなタイミングで自由に行動できるテント泊の醍醐味を満喫してください。
山小屋の場合、消灯時間は20〜21時前後が一般的です。テント場には決まりはありませんが、基本は同様。周囲に迷惑をかけないよう、遅い時間まで大声で談笑することは慎みましょう。夜中にトイレに行く場合なども、他人のテントをヘッドランプで直接照らすなど安眠を妨げてしまう行為は避けて下さい。
翌朝は時間に応じて朝食を済ませて、テントを撤収して出発します。前夜のうちに翌日に必要な水を確保したり、パッキングしやすいようにテント内を整理整頓しておくと、スムーズに出発できますよ。
初心者でも安心&快適!日本アルプス・おすすめのテント場紹介
しめくくりに、初心者でもおすすめのテント場を紹介します。今回は北アルプスから、比較的大規模でテントを設営しやすい3箇所をピックアップしました。
雷鳥沢キャンプ場|立山連峰

立山黒部アルペンルートで標高2,450mの室堂まで楽々アクセス。そこから雄大な立山連峰、ミクリガ池・ミドリガ池の神秘的な水鏡、高山植物のお花畑を楽しみつつ石畳の遊歩道を歩いて約1時間の場所にあるのが雷鳥沢キャンプ場です。
大汝山(3,015m)を最高峰とする立山連峰へのベースキャンプに最適なだけでなく、室堂周辺の遊歩道をハイキングしたり、夕日に染まる立山連峰を眺めるだけでも充実したテント泊を楽しむことができます。途中にある山小屋・みくりが池温泉や雷鳥荘では、室堂直下にある地獄谷から湧き出した源泉かけ流しの湯を、日帰り入浴でも楽しむことができます。
(おすすめは、下記モデルコースの逆回りが便利です)
双六小屋テント場|双六岳

広い平原状の山頂の彼方に槍ヶ岳がそびえる絶景が「天空の滑走路」として人気の双六岳(2,860m)と槍ヶ岳へ続く樅沢岳(2,755m)の鞍部に位置するのが双六小屋テント場です。近くにある双六池の静かな水鏡の向こうには笠ヶ岳を望むことができ、さながら天空のオアシスです。
裏銀座縦走路や黒部川源流・雲ノ平など長距離縦走の起点として利用する人も多いテント場ですが、双六岳の往復でも北アルプスの絶景を存分に堪能できます。新穂高温泉から続く小池新道は、しっかりと整備された歩きやすい登山道。途中にわさび平小屋・鏡平山荘の2軒の山小屋があるのも初心者に安心な理由です。
涸沢野営場|穂高連峰

テント泊登山をめざす人の憧れの場所のひとつが、穂高連峰に囲まれた氷河圏谷・涸沢カールです。奥穂高岳(3,190m)・北穂高岳(3,106m)のベースキャンプとしても好適ですが、いずれも険しい岩稜。朝焼けに染まるこれらの山々を背景に広がるお花畑や紅葉を眺めるために、涸沢だけを訪れる登山者も数多くいます。
上高地からの道のりも横尾まではほぼ平坦で、そこから先も整備が行き届いた登山道が続きます。テントの中で寝転びながら、あるいは隣接する涸沢ヒュッテ・涸沢小屋の2軒の山小屋のテラスでお酒や軽食を楽しみながら、日本を代表する山岳風景を眺める贅沢な時間を楽しむことができる場所です。
今年は日本アルプスのテント泊で夏山登山を満喫しよう!

今回は初めてのテント泊に備えて、基本的な装備・持ち物から便利グッズ、テント泊の楽しみ方までを紹介しました。
テントに宿泊することでしか得られない自然との一体感…初心者でもその魅力を満喫することのできるテント場も多い絶景尽くしの日本アルプスで、今年の夏山登山を満喫してください。

鷲尾 太輔
登山の総合プロダクション・Allein Adler代表。山岳ライターとして、様々なメディアでルートガイド・ギアレビューから山登り初心者向けの登山技術・知識のノウハウ記事まで様々なトピックを発信中。登山ガイドとしては、読図・応急手当・ロープワークなどの「安全登山」をテーマとした講習会を開催しています。